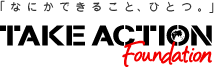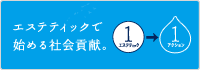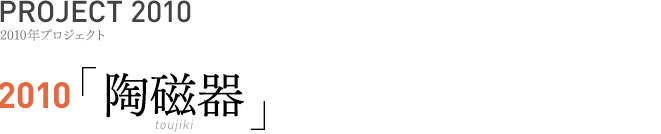
優陶磁器とは、陶土や良質の粘土を主原料とし、これに長石や石英をまぜて焼いて造ったもので、一般的に”やきもの”といわれるものの総称。起源は人類の文化が芽生えた数千年前にさかのぼると言われ、日本においても、中国や朝鮮半島の影響を受けて発達しながら、17世紀以降日本独自の作風がつくり出されるようになりました。原材料や焼成温度などにより分類されており、陶器は粘土、磁器は石の粉末を用います。また、素焼きしたものに釉薬をかけることで風合い変りますが、この釉薬は現在何千もの種類があるといわれおり、陶磁器の可能性の深さを感じることができます。有田、瀬戸、唐津、美濃、笠間、益子、その他にも産地が全国的にあり、その違いを楽しむことができます。
2010年プロジェクト index
![]()
日本の伝統文化や技術の継承と発展を支援することを目的に生まれた、TAKE ACTION のREVALUE NIPPONPROJECT。プロジェクトでは、毎年ひとつの分野をテーマに、有識者によるアドバイザリーボードを結成、各メンバーが注目の工芸家とあらゆる分野のアーティストを選出しコラボレーションで作品を制作することにより、その過程や、異なるジャンルの競演から生まれる新たな魅力を伝え、工芸に新たな可能性を見出すことを目的としています。
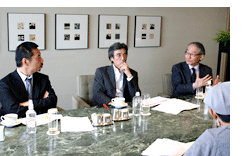 2010年、プロジェクト初年度のテーマに選ばれたのは、”陶磁器”。現代陶芸論の第一人者といわれる金子賢治氏、21世紀美術館秋元雄史氏、ストリートカルチャーのカリスマである藤原ヒロシ氏、日本の編集者松岡正剛氏といった各界の権威をアドバイザリーボードとして迎え、各アドバイザーが選んだ工芸家と、アーティストによるコラボチームを編成、各チームが素晴らしい作品を制作してくれました。
2010年、プロジェクト初年度のテーマに選ばれたのは、”陶磁器”。現代陶芸論の第一人者といわれる金子賢治氏、21世紀美術館秋元雄史氏、ストリートカルチャーのカリスマである藤原ヒロシ氏、日本の編集者松岡正剛氏といった各界の権威をアドバイザリーボードとして迎え、各アドバイザーが選んだ工芸家と、アーティストによるコラボチームを編成、各チームが素晴らしい作品を制作してくれました。
秋元雄史監修 見附正康 × 佐藤オオキ
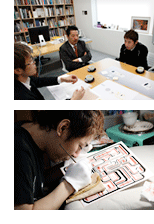 秋元雄史氏が選んだのは、石川・九谷焼の伝統技術である「赤絵細描」で注目の若手・見附正康さんと、海外でも幅広く活躍するクリエイターの佐藤オオキさん。赤絵細描とは、白磁胎の上に極細の筆で髪の毛よりも細い赤い線を描き詰め、文様を作り上げていく、上絵付技法のひとつ。赤一色、あるいは金彩などを加えて描き出されます。
秋元雄史氏が選んだのは、石川・九谷焼の伝統技術である「赤絵細描」で注目の若手・見附正康さんと、海外でも幅広く活躍するクリエイターの佐藤オオキさん。赤絵細描とは、白磁胎の上に極細の筆で髪の毛よりも細い赤い線を描き詰め、文様を作り上げていく、上絵付技法のひとつ。赤一色、あるいは金彩などを加えて描き出されます。プロジェクトの話を聞いて、すぐに見附さんの名前が浮かんだという秋元さんは、そのコンピューターグラフィックのような精密な赤絵を、“今”に落とし込むデザイナーとして、佐藤さんに声をかけました。“アナログとデジタルの見直し”“伝統技術のコンパートメント”といったテーマで、佐藤さんが提案したのは、セラミックのスピーカー。
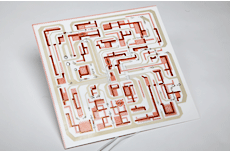 見附さんの「限りなく精緻」な赤絵技術を活かすための、コンピューターによる「完全に精緻」な加工との融合でした。「茶器や花器、大皿といった作品を手がけてきた自分にとって、秋元さんや佐藤さんの斬新なアイディアは、驚きや楽しい経験となった」と語る見附さんは、厚さを1mm以下に削った陶板の電子回路をキャンバスに、息を呑むような美しい赤絵文様を彩ってくれました。
見附さんの「限りなく精緻」な赤絵技術を活かすための、コンピューターによる「完全に精緻」な加工との融合でした。「茶器や花器、大皿といった作品を手がけてきた自分にとって、秋元さんや佐藤さんの斬新なアイディアは、驚きや楽しい経験となった」と語る見附さんは、厚さを1mm以下に削った陶板の電子回路をキャンバスに、息を呑むような美しい赤絵文様を彩ってくれました。金子賢治監修 和田的 × 佐藤卓
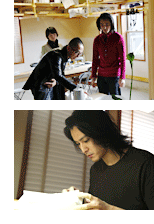 本プロジェクトを“工芸の世界に新しい風が吹くと感じた”という金子賢治さんは、超現代的なフォルムで伝統工芸の枠を超える作品を生み出す和田的さんと、これでまで数多くのヒットを生み出してきたグラフィックデザイナーの佐藤卓さんをコラボレーション。端正かつモダンな作品を手がける和田さんは、磁器を彫刻刀で削り、フォルムを完成していきます。
本プロジェクトを“工芸の世界に新しい風が吹くと感じた”という金子賢治さんは、超現代的なフォルムで伝統工芸の枠を超える作品を生み出す和田的さんと、これでまで数多くのヒットを生み出してきたグラフィックデザイナーの佐藤卓さんをコラボレーション。端正かつモダンな作品を手がける和田さんは、磁器を彫刻刀で削り、フォルムを完成していきます。卓越した集中力で、シャープな角度や線を作り上げるその真摯な姿勢を高く評価した佐藤さんは、和田さんが作る香炉に、長体・平体をかけることを提案。5つが1セットとなる香炉たちの、その変化は、何と、ひとつずつのサイズを00%、00%という細かい数字を佐藤さんが指定。
 手作業で削るという手法ながらに、それに応えることのできる和田さんの緻密な作業には驚くばかりです。
手作業で削るという手法ながらに、それに応えることのできる和田さんの緻密な作業には驚くばかりです。完成した作品は、凛とした美しい香炉が整然と並び、サイズの変化による表情の違いを楽しめる作品となりました。まさに、佐藤さんの計算と和田さんの技術が見事にコラボレーションしています。
藤原ヒロシ監修 新里明士 × 宮島達男
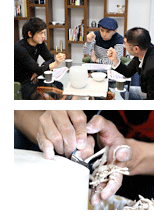 ミスマッチやアンバランスな結合に魅力を感じるという藤原ヒロシさんが選んだのは、無数に開けられた穴から光がこぼれる磁器「光器」シリーズの新里明士さんと、デジタルを駆使したアートを発表し続ける宮島達男さん。
ミスマッチやアンバランスな結合に魅力を感じるという藤原ヒロシさんが選んだのは、無数に開けられた穴から光がこぼれる磁器「光器」シリーズの新里明士さんと、デジタルを駆使したアートを発表し続ける宮島達男さん。
新里さんの作品を一目見てデジタルっぽいと感じた藤原さんは、コラボレーション相手として、直感的に宮島さんを選出。新里さんの作品に宮島氏のデジタルが浮かび上がるイメージがすぐに浮かんだという藤原さんの意向を伝えると、初回の打ち合わせから全員の意見が大いに交わされました。
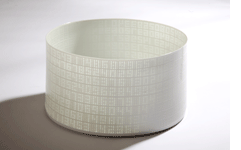 互いに妥協をせず、ぶつかりあって新しいものを生み出そうとした二人のアーティストが、お互いを尊重試合、一致するところを重ねあって生み出された作品は、これまでの新里さんの作品とも大きく異なる、新たなメッセージを伝えるものとなりました。
互いに妥協をせず、ぶつかりあって新しいものを生み出そうとした二人のアーティストが、お互いを尊重試合、一致するところを重ねあって生み出された作品は、これまでの新里さんの作品とも大きく異なる、新たなメッセージを伝えるものとなりました。松岡正剛監修 林恭助 × 町田康
 日本文化研究の第一人者といわれる松岡正剛さんがこのプロジェクトで選んだのは、800年間誰もできなかった技術「曜変天目」の復元に成功した林恭助さんと、パンクロッカーでもあり芥川賞受賞作家である町田康さん。岐阜・土岐にある林さんの工房を松岡さんと町田さんが訪れ、決められたのは、黒織部の作品を作ること。
日本文化研究の第一人者といわれる松岡正剛さんがこのプロジェクトで選んだのは、800年間誰もできなかった技術「曜変天目」の復元に成功した林恭助さんと、パンクロッカーでもあり芥川賞受賞作家である町田康さん。岐阜・土岐にある林さんの工房を松岡さんと町田さんが訪れ、決められたのは、黒織部の作品を作ること。織部とは、千利休の後で茶の湯の第一人者と呼ばれた古田織部が好んだといわれる焼き物で、土岐はその地元。偶然にも松岡さんは、織部の創造的な発送を現代に甦らせることをコンセプトに開催されていた「織部賞」の総合プロデュースも勤めていました。鉄釉を施し焼成が完成した際に窯から引き出し急冷、鉄釉を漆黒色に発色させる“引き出し黒”という技法で、茶碗の図柄を松岡さん・町田さんが担当。
 陶芸作品に触ったことがなく、伝統といかに向き合っていくかということに当初戸惑いを感じていた町田さんですが、次々と独創的なアイディアが湧き出た様子で絵を施していきました。作品を収める木箱には、図柄を書いていない人が箱書きをするという、面白い工夫もされました。町田さんが手がけた図柄の作品に名をつければ、松岡さんがそのストーリーをイメージして箱書きを施す、そしてその過程は、実は林氏によりプロデュースされるというもの。まさに3者が楽しみながらコラボレーションして作品が生み出されました。林さんの工房「一指庵」にちなんで「三指組」を記した袱紗も収められています。
陶芸作品に触ったことがなく、伝統といかに向き合っていくかということに当初戸惑いを感じていた町田さんですが、次々と独創的なアイディアが湧き出た様子で絵を施していきました。作品を収める木箱には、図柄を書いていない人が箱書きをするという、面白い工夫もされました。町田さんが手がけた図柄の作品に名をつければ、松岡さんがそのストーリーをイメージして箱書きを施す、そしてその過程は、実は林氏によりプロデュースされるというもの。まさに3者が楽しみながらコラボレーションして作品が生み出されました。林さんの工房「一指庵」にちなんで「三指組」を記した袱紗も収められています。中田英寿監修 奈良美智 × 植葉佳澄
 このプロジェクトで陶磁器の作品を作ることが決定した頃から、中田の頭に浮かんでいたのは“土鍋”。「どうして土鍋って決まりきった色や形しかないのだろう?」そんな疑問からスタートした中田は、存在感のある鍋を作りたいと、思い描いていました。
このプロジェクトで陶磁器の作品を作ることが決定した頃から、中田の頭に浮かんでいたのは“土鍋”。「どうして土鍋って決まりきった色や形しかないのだろう?」そんな疑問からスタートした中田は、存在感のある鍋を作りたいと、思い描いていました。奈良美智さんが最近陶芸をしているという噂を聞きつけた中田は、すぐに奈良さんにオファー。奈良さんに快諾いただき、そのコラボレーション相手として選出したのが、日本の伝統的な図柄や絵付けの勉強・研究を重ね、独自の世界観を作り出してきた植葉佳澄さん。偶然にも、知り合いだったという二人は、初回の打ち合わせから盛り上がり、デッサン画を描きながら、アイディアをぶつけ合いました。
 その後、滋賀のアーティスト・イン・レジデンスに滞在して、土鍋の成形から絵付けまで、すべてを共同で創り上げる二人のもとを中田が訪れると、そこで目にしたのは、中田が想像もしなかった巨大な土鍋をはじめとするたくさんの土鍋。奈良さんと植葉さんが親しみを持てるものを作りたいと、楽しみながら制作した様子が見て取れる、ユニークでキュートな土鍋たちでした。この土鍋たち、二人が楽しみながら創り上げてくれる様子に中田も大層喜び、またアイディアを重ねながら、完成されました。
その後、滋賀のアーティスト・イン・レジデンスに滞在して、土鍋の成形から絵付けまで、すべてを共同で創り上げる二人のもとを中田が訪れると、そこで目にしたのは、中田が想像もしなかった巨大な土鍋をはじめとするたくさんの土鍋。奈良さんと植葉さんが親しみを持てるものを作りたいと、楽しみながら制作した様子が見て取れる、ユニークでキュートな土鍋たちでした。この土鍋たち、二人が楽しみながら創り上げてくれる様子に中田も大層喜び、またアイディアを重ねながら、完成されました。